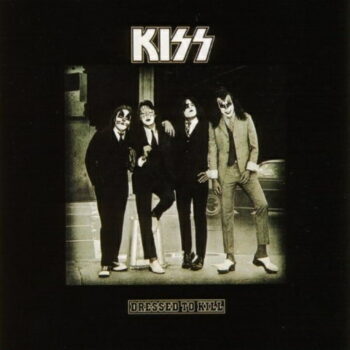Iron Maiden / The Number of the Beast レビュー
まさかのヴォーカル交代に戸惑いながら恐る恐る聴いた新作
1982年リリースのアイアン・メイデン3枚目のアルバム(邦題:魔力の刻印)。
1980年にデビューアルバム「鋼鉄の処女」をリリース後、翌1981年に2ndアルバム「Killers」、そして3rdアルバムの本作と、毎年コンスタントに新譜をシーンに送り出してくる理想的なペースで、バンドは文字通り波に乗っていました。
そんな中で本作の最大のトピックは何と言っても、ヴォーカルがポール・ディアノからブルース・ディッキンソンに交代というショッキングな大事件を経て作られた作品だということです。
ドラゴンボールの「フリーザ」や「セル」で言ったら「第2形態」っつう感じでしょうか。
ポール・ディアノのバンド脱退(解雇?)理由は、スティーブ・ハリスのパンク嫌いうんぬんとか?。
その辺りのゴシップネタは散々色々な方々が語っていらっしゃいますので、今更私が記す必要もありませんね。
なので、私はこのアルバムを初めて聴いた時に感じたことだけを記します。
私の持った第一印象。
「げげっ!。なんだよこの音痴ヴォーカルは?!。終わったなメイデン。」
この一言につきます。
少し話がそれますが、かつて「おニャン子クラブ」や「AKB48」を世に送り出してきた稀代のプロデューサー秋元康氏が、音楽マーケティング的に成功した要因を自ら語っていたことがありますが、大事なのは「予定調和をちょっとだけ崩すこと」だと。
お客さん、リスナー、視聴者が予測しうるところから少しだけあえて外して表現すると、脳にとっては強烈にインパクトが残り、その刺激によってより強固にインプットされるようになるとか言ってました。
言わんとする所は何となく理解できるような…。
ヴォーカルで言えば想定を超える「音域」の表現だったり、独特の声質による「音質」の表現だったり、ちょっと意表を突く想定外のメロディラインだったり。
こちらの経験値からなる無意識の予測の範囲をちょっとだけ外れたり、超えてきたりすると「ん?」「何かちょっと違うな」「良いな」となって強く印象に残るんだと思います。
しかしながら、この新ヴォーカルのゴリラ、いや、ブルース・ディッキンソンのヴォーカルスタイルに関しては、声質、高音、歌唱法とかうんぬんの前に、そもそも終始「音程」が外れまくってねーか?て感じ。
「ヴォーカルメロディが定まってないでしょーよ!」
というのが初めて聴いた時の率直な感想でした。
宮川大輔風に言うならば、「これ絶対毎回歌うたんびに微妙に違うメロディで歌う奴やん。」というのが第一印象だったのです。
音楽的な素養に乏しい当時の純粋な青年にとっては、予定調和どころか基本メロディを堂々と外して我が道を突き進んでいくようなヴォーカルスタイルには全くついていけませんでした。
当時の「外しヴォーカル」でせいぜい許容できたのはグレン・ヒューズ辺りまででしょうか。
(さりとて、そんなに外してはいませんでしたが)
当然のことながら、事前にブルース・ディッキンソンの身辺調査として、SAMSONを聴いて予習しておくほどの財政的な余裕もある筈もなく、突然に突きつけられたあまりに衝撃的なヴォーカルスタイル。
これにはさすがにアナフィラキシーショック級のアレルギー反応を起こしてしまいましたね。
後にSAMSONを後追いしてみると、全く外してる感など無く非常に聴きやすいメロディだった印象があります。
既にその頃にはブルース節に耳が慣れていた(侵されていたともいう)ものとも思われますが。
人間関係においても、第一印象で嫌な印象を持った人ほど時間を掛けて関係構築していくと、より深淵な関係になることがあると言われています。
本作以降のアイアン・メイデンのアルバムについても、作品を聴き重ねていくに連れ、ブルース・ディッキンソンのヴォーカル=何の違和感もなくアイアン・メイデンそのもの、と言った確固たる予定調和が形成されていくことになるのでした。
それにしても、初対面でのあの風貌とクセが強すぎる(もはやクセしかない)ヴォーカルスタイルを、自分のなかで咀嚼~消化するまでにはそれなりの時間が掛かったように思います。

6分超の大作が3曲も収録~じっくり腰を据えて聴くアルバム
あまりのヴォーカルの変貌ぶりに打ちひしがれつつも、貴重なお小遣いで買ったアルバムですから聴き込まない訳にはいきません。
自身もバンドの真似事程度にギターをやっていたこともあり、どうにも受け入れ難いヴォーカルをまるで避けるかのように、各楽器パートを妙に集中して聴いてみたりしていました。
また、アイアン・メイデンの真骨頂は、デビュー当時から「楽曲展開の妙技」ですよね。
本作でもそのドラマティックな展開に酔いしれながらひたすら何度も何度もアルバムを聴き込みました。
特に本作には曲の長さが6分を超える大作が3曲も収録されており、そのドラマティック性に富んだ世界観とテクニカルな演奏を堪能するには、じっくりと腰を据えて神経を集中して聴き込まないといけなかったアルバムと言えるでしょう。
(よく言われる〇周目くらいから良さが解ってきたとかいう状態)
とにかく最初の内は、何かしながらのBGM程度の腰掛け聴きではなどもっての外。
真剣勝負で聴き込まないと到底太刀打ちできないような強敵だったのを思い出します。
メンバー・収録曲
【メンバー】
- ヴォーカル: ブルース・ディッキンソン
- ギター : デイブ・マーレイ
- ギター : エイドリアン・スミス
- ベース : スティーブ・ハリス
- ドラム : クライブ・バー
【収録曲】
- Invaders
- Children Of The Damned
- The Prisoner
- 22 Acacia Avenue
- The Number Of The Beast
- Run To The Hills
- Gangland
- Total Eclipse
- Hallowed Be Thy Name
おすすめ楽曲
当然のことながら、もはや全曲おすすめなのですが今回は熟考に熟考を重ねつくした厳選ですということで、「Run to the Hills」 のようなあまりにもメジャーな楽曲は外しています。
Children Of The Damned
オープニング曲でのぶちかましを経て、アコスティックイントロ~スローテンポでじっくり聴かせる、まるで「リメンバー・トゥモロー(=ポール・ディアノ)」との決別を意識的に表現しているかのような楽曲ですね。
圧巻はギターソロ前のスピードアップを伴う展開変化があるビルドアップ部分。
勢いをそのまま保ちながら、ハモリのツインソロへなだれ込むまさにメイデン節。
必勝方程式通りの展開に、陳腐な表現ではありますがホントに鳥肌が立ちます。
The Prisoner
この曲は何と言ってもクライブ・バーのドラミングが冴えわたっています。
イントロのバスドラのタメを効かせた刻みからの、疾走感を重視した余計なおかずとシンバルを極力控えめにした小気味良さには、背中がゾクゾクするような緊張感を覚えます。
無駄な個人プレーに走らずにフォア・ザ・バンドに徹した献身的なプレイが光り、楽曲の完成度を一気に引き上げる立役者となっていると思います。
そしてこれまた盤石の方程式通りのギターソロからの曲展開が見事です。
デイブ・マーレイって顔に似合わずホント綺麗なフレーズ繰り出してきますよね(失礼)。
22 Acacia Avenue
曲調としては初期の前2作の流れを色濃く残しつつも、変幻自在の曲展開によるドラマティック性には新境地に足を踏み出したかのような確かなレベルアップを実感できる名曲。
もはや舞台演劇を見ているかの如く、次々と脳裏に情景が浮かんでくるような不思議な感覚に襲われます。
間違いなくこれまでのヘヴィメタルというジャンルにおいて、誰も成し得なかった世界観の表現であり、アイアン・メイデンというバンドの恐るべき懐の深さ、センスと実力に屈服させられます。
The Number Of The Beast
イントロからの複雑なリズム展開に戸惑いながら、目まぐるしく展開されるスティーブ・ハリスのベースラインを必死に耳で追いかけるもはやクセがついてしまいました。
へんてこな変拍子を全然力まずに淡々とクールに刻んでいくクライブ・バーのドラムも心地良いです。
これって絶対に「アマチュアバンドにコピーさせない意地悪曲だろっ!」と自らのテク不足を棚に上げて勝手に憤慨しつつ、逆に「こうなったら死んでも絶対にコピーしてやるぞ!」という意味不明の反骨心?闘志が燃えてきました。
それにしても当時の小僧にとってはイントロから続くリフをダウンストロークのみで正確に刻むだけでも、妙に力んじゃって結構な筋力を使う曲でした…。
バイト代を貯めてようやく買ったフランジャーなんかもいじくりながらどうにかそれっぽく誤魔化せるくらいまではいったけど、結局ベースがギブ・アップしてTHE ENDでした。
残念…。
Hallowed Be Thy Name(審判の日)
この曲の素晴らしさに気づけたのは結構時間が経ってからでした。
再生何周目ころだったでしょうか。
ただでさえ曲長さ7分11秒という長丁場の闘い。
緊張感MAXのイントロから、憂いはあるもののどちらかと言えば単調な曲の序盤。
そして何よりも「アルバムラストの配置」ということで、相当スタミナを温存した状態でこの曲にたどり着かないと太刀打ちできない難攻不落の楽曲でした。
かと言って、この曲を単発で聴こうという気にもなれず、あくまでもこのアルバムの締め括りとして聴かないと気が済まない変な拘りを持ってしまう不思議な曲でした。
曲の終盤に向かってのいつものドラマテックな曲展開の変化~スピードアップ~ギターソロにかけては、本作の中でもやはりずば抜けた完成度と最高に格好良い構成と言えるでしょう。
ワウを効かせたトリルのソロフレーズは、このアルバム辺りでデイブ・マーレイの代名詞的なものとなりました。
まとめ
恐るべしスティーヴ・ハリスの先見の明
3枚目のアルバムにして、ポール・ディアノの脱退から元SAMSONのブルース・ディッキンソンの加入という大勝負に打って出たアイアン・メイデン。
NWOBHMムーブメントに乗っかって人気もうなぎ上りの中での、バンドのフロントマン(顔)の変更だけに本作には特別な注目が集まりました。
音楽的な素養と感受性に乏しかった私には、ブルース・ディッキンソンのヴォーカルスタイルを受け入れるのにかなりの時間が掛かってしまいましたが、すんなりとスムーズに受け入れた方々も多かったことでしょう。
まあ、人間誰しも(大抵の人)は変化する事には少なからず抵抗というかストレスを感じてしまうもので、それらの多くは「時間」と「慣れ」が解決してくれるものです。
初めて聴いた時に目の前が真っ暗になり「終わった感」しかなかったブルース・ディッキンソンのヴォーカルも、いつの間にやら違和感がなくなり、やがては後のブルース・ディッキンソンの脱退による更なるヴォーカル変更時には「やはりヴォーカルはブルースでないと…」となるのですから、現金なものです。
今こうして改めて考えてみれば、この後に立て続けに輩出されることになるアイアン・メイデン絶頂期の作品群は、ポール・ディアノがヴォーカルのままでは到底産み出せなかっただろうなと、あくまで結果論ですが納得しちゃいます。
既に、当時の段階でそれを見越してポール・ディアノに見切りをつけたスティーブ・ハリスの歴史(先見)を読む力。
恐るべしです。