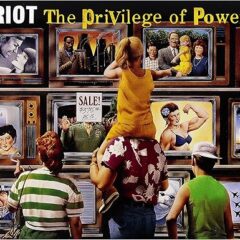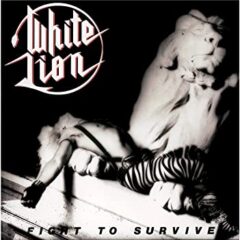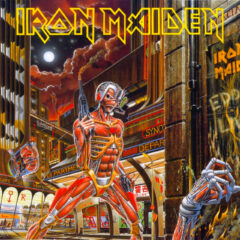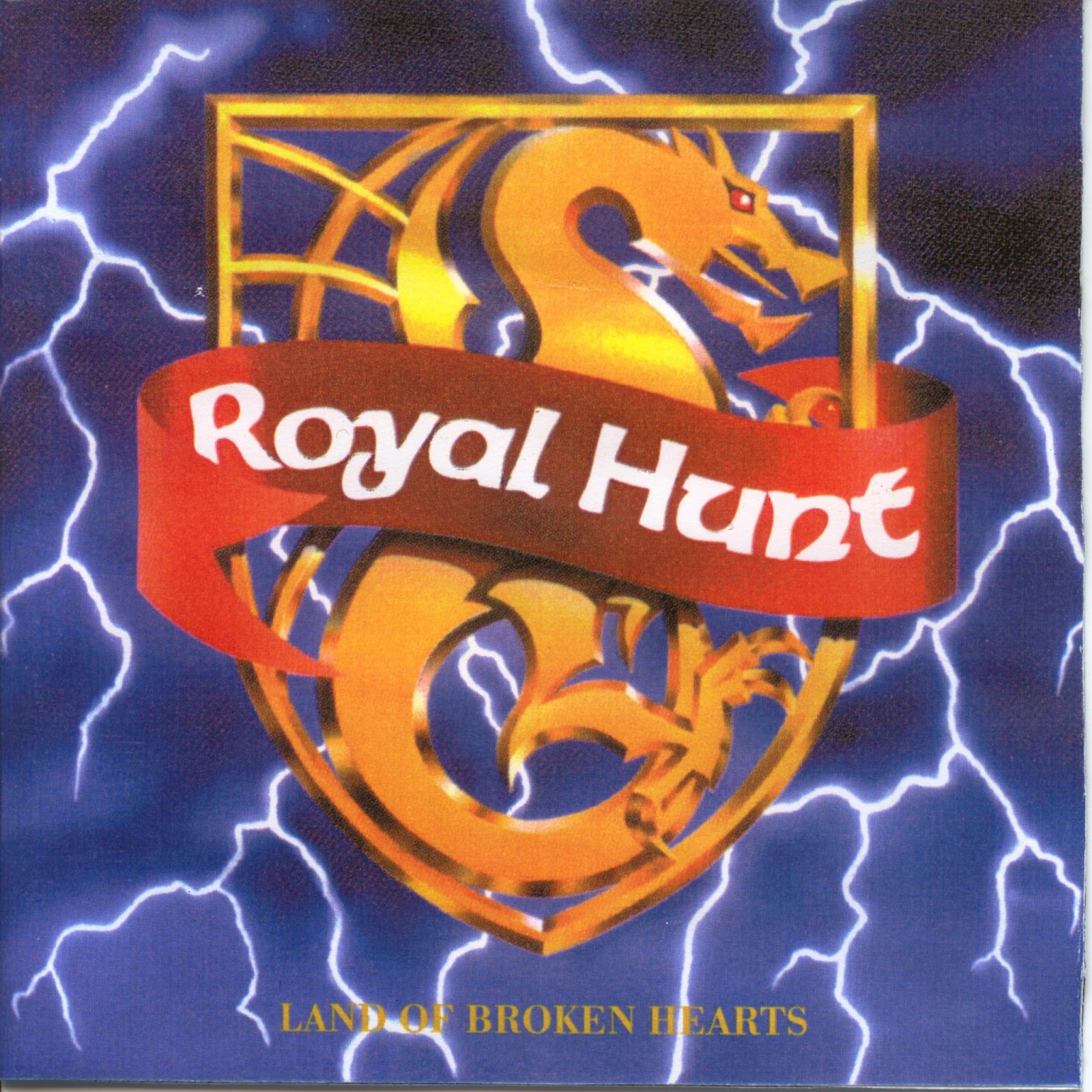PRAYING MANTIS / KATHARSIS レビュー
カマキリ怪獣は姿を消し期待膨らむ大袈裟なジャケット
NWOBHMムーヴメントの代表格バンド PRAYING MANTIS の約4年ぶりとなる12枚目のアルバム「KATHARSIS」です。(2022年1月28日リリース)
タイトルからして意味深な感じで気合い入ってますね。
辞書を開けば「人の心に怖れと憐あわれみを呼び起こし、その感情を浄化するという効果」「アリストテレスが「詩学」で展開した言葉」などと記載があります。
こ、これは、近年の前2作品で迷走の兆しが見られたバンドの音楽性が、一気に明確に解き放たれてヘヴィメタル(PRAYING MANTIS)ファンのモヤモヤ感が綺麗に浄化される作品なのでは?。
ジャケットデザインもバンドロゴはそのまま継承されてはいるものの、カマキリ怪獣は姿を消しています。
そして、神により心を解放された人々をイメージするかのような大仰なデザインが施されており、敬虔なPRAYING MANTIS信者を自負する私の期待値はうなぎ上りに高まりました。
想定外のポップ路線にビックリ!
結論から言いましょう。
「PRAYING MANTISはヘヴィメタルバンドではなくなりました」。
ハッキリ言って、本作を1周聴き終えただけでは PRAYING MANTIS というバンドが一体何を目指しているのか「ビジョン」や「方向性」が全く分からなくなってしまいました。
それは恐らくPRAYING MANTISと共にリアルタイムで併走してきた過去の音楽性イメージがあまりにも強すぎて、進化、変化することに対する一種のアレルギー反応という要素が大きいのかもしれません。
(昔はこうだった、ああだったと言ってても何の進歩も無いですよね…。)
全てとは言いませんがかなりハードポップ化しましたね~。
とは言え、私は決してハードポップ・バンドを否定するものではありません(むしろ大好物)。
あくまで PRAYING MANTIS がこれをやる必要があるのか?という見地からの意見です。
もっと言ってしまえば、得意とする日本マーケット向けの楽曲として「まあこんなもんだろ」的な安直な楽曲作りをしているのが透けて見えるようで…。
しかしながら2周目、3周目と聴き込んでいくうちに、徐々に本作の音楽性こそが現在のPRAYING MANTISの明確な立ち位置であり見据えている音楽性なのだなと思えるようになりました。
妄信はいけませんが、PRAYING MANTIS 愛が強いので余程でない限り最終的には好きな作品になっちゃいますね。
バンドとして「進化」なのか? 今後問われる「真価」
それにしても、往年の古参ファンがイメージするPRAYING MANTIS像だけを求めてはいけない時代に入ったのだなと改めて思います。
あくまでもここで記しているのは私の個人的な主観ですので、全く違った捉え方で本作に対するアプローチをするファンの方々も多いことと思います。
かつて、泣きメロ総合商社などと勝手にネーミングさせて頂き、古き良き英国の伝統を受け継ぐツインリード・ギターを中心に据えたヘヴィ&キャッチーな楽曲を量産していたバンド「PRAYING MANTIS」。
近年の前々作辺りから徐々に垣間見えていた「ポップ化」の潮目は、本作で一気に加速しかつてのヘヴィメタルバンドとしての残像は幻のように薄れてきています。
今後のマーケットにおける反応(実績)、色々な人々のレビュー、感想などを見守って本作の「真価」を見極めていきたいと思います。
バンドの代名詞「メンバーチェンジ」は終息
PRAYING MANTISといえば、とにかくトロイ兄弟以外のメンバーが目まぐるしく変わる「メンバーチェンジ」がバンドの代名詞。
しかし、ここ最近のアルバムではようやくメンバーが固まりつつある状況で、前々作「LEGACY(2015年)」から変動はありませんね。
逆にいうと、このことが前々作辺りから顕著になり出した「ハードポップ化」に一層の拍車を掛けてその加速度が増した要因のような気がします。
メンバー・収録曲
バンドメンバー
- ヴォーカル: ジョン・ジェイシー・カイペルス
- ギター : ティノ・トロイ
- ギター : アンディ・バーゲス
- ベース : クリス・トロイ
- ドラム : ハンス・イン・ザント
収録曲
- Cry For The Nations
- Closer To Heaven
- Ain’t No Rock ‘N’ Roll In Heaven
- Non Omnis Moriar
- Long Time Coming
- Sacrifice
- Wheels In Motion
- Masquerade
- Find Our Way Back Home
- Don’t Call Us Now
- The Devil Never Changes
おすすめ楽曲

Cry For The Nations
HR/HMファンにとっては聖域とも言える「曲名」をいきなりぶっ込んできましたね。
この曲名を使用するのは、ACミランで背番号10番を付ける位の覚悟と図々しさが求められると思います。
しかし、そこは流石の重鎮バンド。
こちらもあの名曲に負けじ劣らじの楽曲ではあーりませんか。
悲し気なピアノのイントロで始まるオープニングに相応しい「プレマン節」全開の名曲ですね。
本作総じての印象ですが、ギターがかなり奥に引っ込んだミキシングで派手なソロも一切無しです。
Closer To Heaven
出ました。
若干の憂いは僅かに残すものの、基本路線は爽快アメリカン・ハードポップな一曲。
目隠しで聴かされたら絶対に「PRAYING MANTIS」と的中させる人はいないと断言しちゃいます。
これは、GIANT、SURVIVOR辺りを連想してしまいそうな楽曲ですね。
これをPRAYING MANTISがやる必要あるのか?という議論が巻き起こりそうな楽曲ですが、素直に良い曲なので有難く感謝しながら受け入れることとします。
Non Omnis Moriar
「プレマン節」を基軸としながらも、変化をつけたアレンジのリズム隊が印象的ですね。
この辺りに「進化」のエッセンスを散りばめながらサビメロは思いっきりド演歌状態のコテコテ感。
それにしても本作、ギターはこれでもかという位に弾きませんねー。
まるで試合中に拳を痛めてしまったボクサーのような封印ぶりです。
ここまで弾かないとやはり若干のフラストレーションが溜まってきてしまいます。
Long Time Coming
これまたかつてのPRAYING MANTISとしては考えられないハードポップ曲。
完全にマーケットを意識した楽曲ですね。
ただ、アルバムのタイトルやジャケットデザインとの整合性には若干の違和感というか、チグハグ感が否めませんが…。
まあ、あまり堅苦しく考えずにやりたい音楽、曲作りを心を解き放つように思いっきりやるということでしょうか。
売れないとバンドも続けられませんしね…。
The Devil Never Changes
オープニング曲と並んで本作の中で最もかつてのPRAYING MANTIS像に近い音楽性を残した楽曲です。
ウォーォォ!の分厚いコーラスが印象的。
ライブでは大合唱~途中ブレイクしての掛け合いとなること必至ですね。
最後の最後の楽曲でようやく多少は弾いてくれてますギターソロらしいソロ…。
何か、これだけおあずけを喰らうと妙に有難みを感じるものですね。
やはり人間の欲望は無限であり、すぐに有難みを忘れてしまうものです。
普段からギターソロを聴けることにもっと感謝しないといけないのかも知れません。
まとめ
PRAYING MANTISの4年ぶりの新作「Katharsis」は新旧のファンにとって受け止め方が異なってきそうな「変化」に富んだ音楽性となりました。
「変化」が「進化」であったのかどうかは、今後のマーケットの反応とリスナー(ファン)一人一人の多様な受け止め方によってその「真価」が問われることとなるでしょう。
バンドとリスナー(ファン)という関係性において、バンドの目指すビジョンや音楽性、作り上げられた楽曲に対してリスナーがどれだけ共感できるかというエンゲージメントが重要ですね。
平たく言っちゃえば、CD聴いたりライブ行って思いっきり拳振り上げてバンドと一体となれるかどうかですよね。
便利なサブスクの音楽配信サービスは「Apple Music」がおすすめ!
視聴した時にアーティストに支払われる報酬が、他のサービスに比べて断然高い!
だから、応援したいアーティストへの貢献度「大」です。
(その違いは何と! SpoXXXの3倍、 AmaXXXの6倍です…)